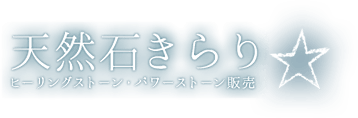ブラジル産水晶で出来ました、縁起物の七福神の置き物で専用の木の台座付きです。









七福神(しちふくじん)は、日本の民間信仰や文化において幸運や繁栄を象徴する七柱の神々のことです。七福神はそれぞれ異なる性格や役割を持ち、幸福、財産、健康、長寿、知恵など、人々の願望を具現化した神々として信仰されています。以下に七福神について詳しく説明します。 七福神の構成 七福神は以下の七柱の神々から構成されています。それぞれの起源や特徴、象徴するものについて解説します。
- 恵比寿天(えびすてん) • 役割・象徴: 商売繁盛、大漁祈願の神 • 由来: 日本由来の神で、伊邪那岐命と伊邪那美命の子である事代主命や蛭子命(ひるこのみこと)とされることが多い。 • 特徴: 鯛を持ち、釣り竿を持つ姿が特徴的。唯一純粋な日本の神。
- 大黒天(だいこくてん) • 役割・象徴: 富貴繁栄、食物の神 • 由来: インドの神「マハーカーラ(大黒)」に由来。仏教を通じて日本に伝わり、大国主命と習合された。 • 特徴: 大きな袋と打ち出の小槌を持つ姿。米俵の上に乗ることが多い。
- 毘沙門天(びしゃもんてん) • 役割・象徴: 武運長久、厄除け、福徳の神 • 由来: インドの神「ヴァイシュラヴァナ」に由来。仏教の四天王の一柱で、多聞天とも呼ばれる。 • 特徴: 武将のような甲冑をまとい、宝塔と槍を持つ。
- 弁財天(べんざいてん) • 役割・象徴: 芸術、学問、財運の神 • 由来: インドの河の神「サラスヴァティ」に由来。仏教を通じて日本に伝来し、日本では水や豊穣の神ともされた。 • 特徴: 琵琶を持ち、美しい女性の姿で描かれることが多い。
- 福禄寿(ふくろくじゅ) • 役割・象徴: 長寿、幸福、財産の神 • 由来: 中国の道教に由来。道教の三徳「福・禄・寿」の一柱。 • 特徴: 長い頭と白い髭が特徴で、巻物を持つ。鶴や亀と一緒に描かれることもある。
- 寿老人(じゅろうじん) • 役割・象徴: 長寿と健康の神 • 由来: 福禄寿と同様、中国道教の神。南極星を神格化したともいわれる。 • 特徴: 長寿を象徴する杖と巻物を持ち、鹿を伴うことが多い。
- 布袋尊(ほていそん) • 役割・象徴: 福徳円満、満足の神 • 由来: 実在した中国の禅僧「契此(かいし)」がモデル。大らかさと満足を象徴する。 • 特徴: 太鼓腹、大きな袋、笑顔が特徴的。
七福神の由来と発展 七福神は日本独自の文化的な組み合わせで、15世紀末から16世紀頃に成立したとされています。日本古来の神仏(恵比寿)と、インドや中国から伝来した神仏(他の六神)が融合して形成されました。室町時代から江戸時代にかけて庶民の間で広く信仰され、七福神巡りが盛んになりました。 七福神巡り 七福神信仰の一環として、七柱の神々を祀る寺社を巡る「七福神巡り」があります。これには、新年に七福神を参拝して一年の幸運を祈願する意味があります。特に以下の地域で有名です: • 東京:谷中七福神、深川七福神 • 京都:都七福神 • 鎌倉:鎌倉七福神 七福神の象徴と文化的意義 七福神は、日本人の信仰心と遊び心が融合した独特な文化の象徴です。それぞれの神が持つ個性が、人々の多様な願いを反映しており、現代でも信仰の対象として、また年始の縁起物として愛されています。